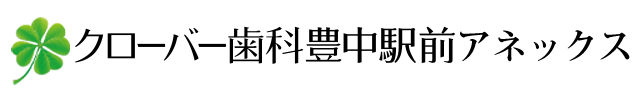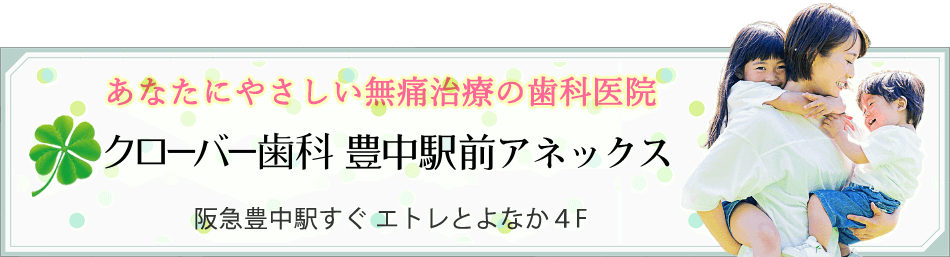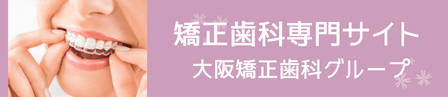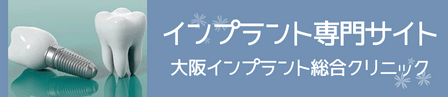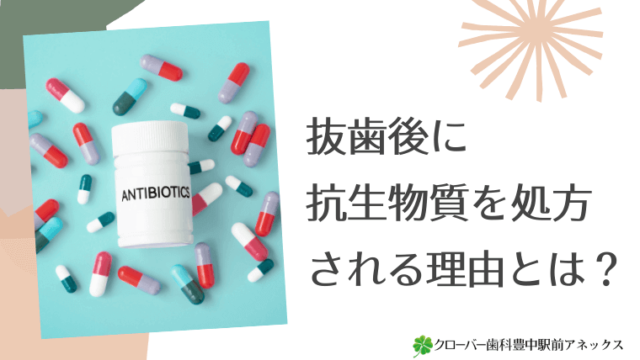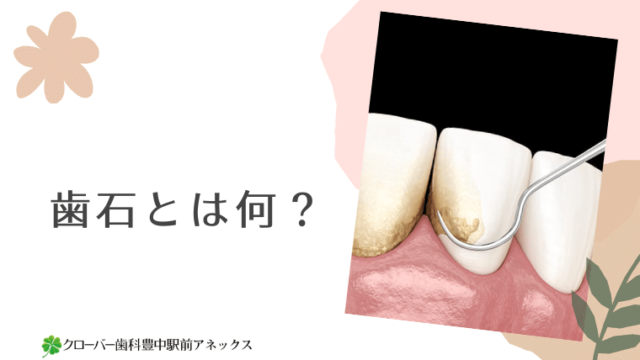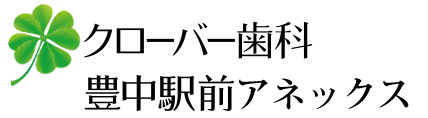歯ブラシの選び方とは

歯ブラシの選び方によって、口腔内の清潔さに差が生じるのか気になる方もおられるでしょう。自分の歯の状態に合った歯ブラシを使用していれば問題ありませんが、そうでない場合、どうしても汚れは残りやすいです。歯ブラシには、毛の柔らかさや固さ、ヘッド(ブラシ部分)の小ささや大きさ等を基準に選択すれば、歯を清潔に健康に保つことができます。
目次
なぜ歯ブラシ選びが重要か
毎日使う道具である歯ブラシですが、適切でないものを使っていると、どうしてもトラブルが起こり得ます。
- 毛先が合っていないことで磨き残しが増え、むし歯や歯周病の原因になる
- 毛が硬すぎて歯茎や歯の根元を傷つけ、知覚過敏や歯茎の退縮を招く
- 毛が柔らかすぎると汚れが落ちにくく、清掃効果が低下する
- ブラシのヘッドや形状が口内の構造と合わないと、届きにくいところができる
歯ブラシの選び方を意識して、自分の口腔状態にフィットする1本を選ぶことは、日常のセルフケア精度を高め、将来の歯科トラブル予防につながります。
歯ブラシには様々な種類がある
歯ブラシには複数の構成があり、それぞれが使いやすさや、清掃効果、快適性に関係します。これらの構造を組み合わせて、自分の口腔環境に合ったものを選ぶことが重要です。
| 構造 | バリエーション | 特徴・適性 |
|---|---|---|
| ヘッドの大きさ | 小型・中型・大型 | 小型は奥や隅に届きやすい。大型は広い面積を一度に磨ける。 |
| 毛の形状 | ラウンド毛・テーパー毛など | ラウンド毛は安全性重視。テーパー毛は小さな隙間に入り込める。 |
| 毛の硬さ | 硬め・普通・柔らかめ | 硬めは力の弱い人にも有効だが力加減注意。柔らかめは歯ぐきに優しいが時間がかかる。 |
| 持ち手 | 細め・太め | 細めはコントロールしやすい。太めはしっかり握れて安定する。 |
| ネック | ストレート・カーブ | カーブは歯列に沿いやすく、角度をつけて磨きやすい。ストレートは磨く力が直接伝わる。 |
自分の口や歯並びに合った歯ブラシの見つけ方
鏡で実際に自分の歯を見ながら、口の形や歯並び、磨き癖を把握することから始めましょう。
ヘッドの大きさを意識する
口の大きさが普通の大人:中型ヘッドがバランスがよく扱いやすい
口が小さく顎が狭い人:小さいヘッドを選んで余裕を持たせる
高齢者や握力が弱い子供:少し大きめのヘッドで一度に磨く範囲を広げる
歯ブラシのヘッドには、さまざまなサイズがあります。一般的な目安としては、上顎の前歯2本分の幅とほぼ同じ大きさのヘッドを選ぶのが理想的です。これが多くの人にとって、バランスの良いサイズとされています。ただし、奥歯を磨く時にえづきやすい方や、1本ずつ丁寧に磨きたい方は、少し小さめのヘッドを選ぶと扱いやすく、隅々まで磨きやすくなります。
毛先の形状と硬さ
歯ぐきが健康であれば普通またはやや硬めの毛でも対応可能
歯ぐきが弱っていたり、炎症がある場合は柔らかめや超やわらかめがおすすめ
歯と歯の間が広い、歯並びに凹凸がある人は先の細いテーパー毛タイプを検討
歯茎が健康な方は、毛の硬さがふつう(レギュラー)の歯ブラシがおすすめです。かためは歯垢の除去力が強いものの、歯茎を傷つけて歯ぐき下がりの原因になることがあるため、できるだけ避けましょう。
一方で、歯茎の腫れや出血などの症状がある方は、刺激の少ないやわらかめを選ぶと安心です。ただし、やわらかい毛は歯垢除去力がやや弱いため、時間をかけて丁寧に磨くことが大切です。歯茎の炎症や出血が治まったら、再びふつうの硬さに戻すのが理想的です。
つまり、健康な歯茎にはふつうの硬さ、炎症時はやわらかめが基本ルールです。
ネックと持ち手の相性
歯列がアーチ状で湾曲している人:カーブネックがブラシを当てやすくする
まっすぐな歯並びの人:ストレートネックでも扱いやすい
歯ブラシのネックと持ち手には、真っすぐなタイプ、軽くカーブしたタイプ、滑りにくいグリップ付きタイプなど、メーカーごとにさまざまな形があります。どの形が一番良いというわけではなく、自分の手にしっくりとなじみ、余計な力を入れずに動かせるものが最適です。まずはいくつか試して、自分に合う形を見つけましょう。
もし選ぶのに迷う場合は、シンプルな真っすぐタイプから始めるのがおすすめです。カーブタイプは奥歯を磨きやすいと感じる方も多いので、その後軽くカーブしたタイプも使い比べながら自分に合う感触を確かめてみてください。持ち手は細すぎても扱いにくく、太すぎても力が入りすぎるので、手の大きさや握力に合った太さを選ぶとよいです。
実際に当ててみる感覚も重視
歯ブラシを選ぶときは、実際にブラシを歯に軽く当ててみて次のような感覚があるかをチェックしましょう。
- 毛先がしなやかにたわむか
- 毛先が歯の隙間やキワに入り込むか
- 持ちやすさや安定性
- 無理な力を入れずにブラシを動かせるか
歯ブラシの持ち方
歯ブラシの持ち方にはいくつかの方法がありますが、代表的なのがパームグリップとペングリップです。
パームグリップ
歯ブラシを手のひら全体で包み込むように握る方法で、安定感があり、しっかりと力を入れやすいのが特徴です。ただし、力を入れすぎると歯ぐきを傷つけたり、毛先が広がったりするおそれがあるため、優しくコントロールしながら磨くことが大切です。
また、この握り方は歯ブラシに力が伝わりやすい反面、細かい動きがしにくいこともあるため、歯面をなでるよう丁寧なブラッシングを心がけましょう。手首に不安のある方や、高齢者や子供など力を入れにくい方には、このパームグリップが向いています。
ペングリップ
ペングリップは、鉛筆を持つように歯ブラシを軽く握る持ち方です。この方法は力の加減がしやすく、ブラシの動きを細かくコントロールできるのがメリットです。手首を使って小刻みに動かせるため、歯と歯の間や奥まった部分をピンポイントで磨くことができます。
一方で、指先の筋力をある程度必要とするため、手の力が弱い方には少し難しい場合もあります。
どちらの持ち方にもメリット、デメリットがあり、重要なのは力を入れすぎず、毛先を歯にやさしく当てることです。自分の手や口の動きに合った持ち方を見つけ、無理なく磨けるスタイルを選びましょう。
磨き残しが起こりやすい部位と補助用具の活用
どれだけ良い歯ブラシを使っても、次のような部位は磨き残しが起こりやすい場所です。
- 歯と歯の間
- 奥歯の咬合面の溝
- 下の奥歯の内側(舌側)
- 上の奥歯の外側(頬側)
- 歯と歯ぐきの境目
- 奥歯の裏側
これらの部位をケアするために、補助用具を組み合わせると効果的です。
ワンタフトブラシ
先端が小さく山のような形のブラシで、歯と歯の間や奥歯の溝、奥歯の裏側などに使いやすいです。
歯間ブラシ
歯と歯の間を清掃する補助用具で、さまざまなサイズがあり、歯ブラシが届かない隙間に使いやすいです。
デンタルフロス
歯と歯の間や、歯肉と歯の間に沿わせて使う補助用具で、卵型やホルダータイプなどがあり、毛先が届かない部分に詰まった汚れや歯垢を掻き出すのに効果的です。
舌ブラシ
舌の上に溜まる舌苔を取り除くには、舌ブラシを使用することが効果的です。やさしく奥から前へ舌苔を除去します。
歯間が狭いのに、無理に歯間ブラシを押し込むと歯周組織を痛める可能性があります。歯間ブラシが入らない隙間はデンタルフロスでケアし、歯ぐきを傷つけないよう角度を調整したり、補助用具を使う順番を決めて習慣をつけるのが良いでしょう。
歯ブラシの交換タイミング
歯ブラシの性能を保つため、定期的な交換と衛生管理は欠かせません。
交換タイミング
歯ブラシは1か月に1回歯ブラシの交換をおすすめします。毛先が開いてきたら、汚れを落とす力が落ち始めますし、風邪や発熱時などの口腔内の菌が増えた時期には早めに交換をしましょう。
使用後のケアや保管方法
- 水ですすぎ、毛並みを整えてから乾かす
- ブラシは風通しの良い場所に立てて保管
- 毛先の接触は不衛生であるため、複数人で同じ容器に立てて置かない
旅行や非常時用ストック
キャップ付き、折りたたみ型などの携帯用歯ブラシを用意しましょう。ただし、キャップや密閉ケースは湿気がこもるとカビや菌の温床になることがあるため注意が必要です。長期保存には乾燥剤と一緒に密閉して保管してください。
よくある誤解や気を付けたい点
歯ブラシ選びや使用にあたって、よくある誤解や気を付けたい点を整理しましょう。
硬めの方が汚れが落ちるは必ずしも正しくない
力任せにゴシゴシこすれば、かえって歯ぐき下がりや歯の表面のエナメル質を傷つける恐れがあります。
安いからダメ、高いから良いわけではない
歯ブラシの形状や毛質、使いやすさが合えば、リーズナブルな製品でも十分に効果を発揮します。
毛先の形状は尖っている方が良いと限らない
テーパー毛はメリットもありますが、力を入れて汚れを掻き出そうとすると、毛先の摩耗が早いです。
力を入れて磨くことときれいに磨けることはイコールではない
適切な角度と動かし方こそが大切であり、強い力をかけ続けて磨くことはむしろ口腔内にダメージを与え続けることになります。
電動歯ブラシに任せきりにしてはいけない
電動タイプでも、使うヘッドや振動種類、使い方を選ばないと十分な効果が出ません。
まとめ

歯ブラシの選び方にはこれが絶対に正解という答えはありません。大切なのは、自分の口腔状態や手の感覚、使いやすさを基準に毎日無理なく使える1本を選ぶことです。口の大きさや歯並びに合ったヘッドと毛質、持ちやすく力を入れすぎない持ち手設計、補助用具との併用、定期的な交換と清潔な保管をしてください。
これが自分に合うと思える歯ブラシを見つけるのが一番ですが、自分に合った歯ブラシが分からない場合は、歯科医院や歯科衛生士に相談してあなたに合う歯ブラシはどのようなものかおすすめしてもらうのも良い方法です。