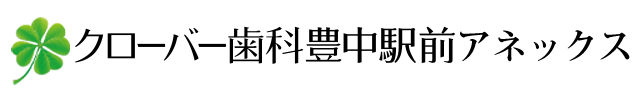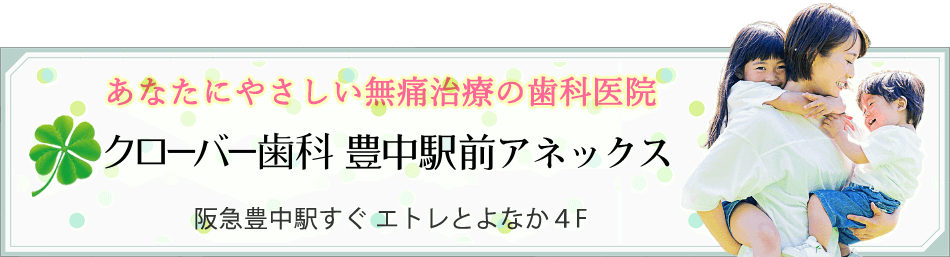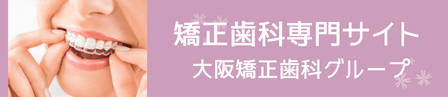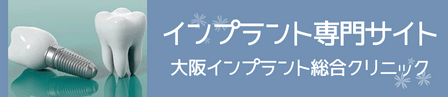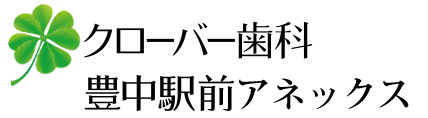床矯正とはどんなもの?
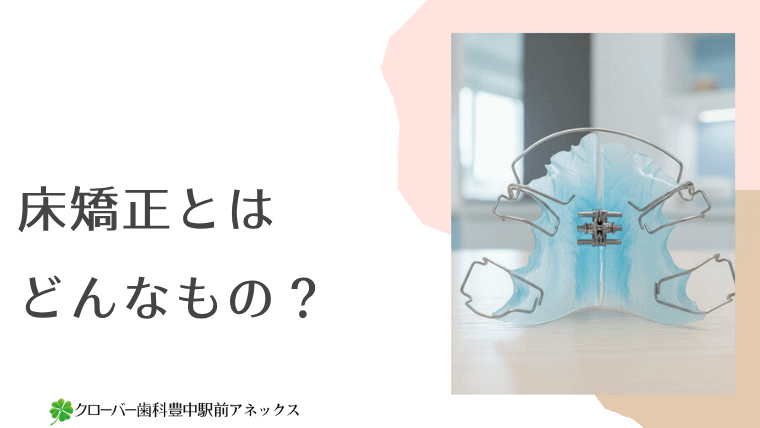
床矯正(しょうきょうせい)という治療法について、聞いたことはありませんか。床矯正は、乳歯のある頃に、将来の永久歯が綺麗に並ぶスペースを確保しようという治療法です。どのような仕組みなのか、メリットやデメリットはあるのかについても詳しくご紹介いたします。
床矯正とは
床矯正は子どもの成長期を利用して、顎の幅や骨格を補正し誘導しながら将来の永久歯がきれいに並ぶスペースを確保しようという治療法です。通常のワイヤー矯正とは異なり、顎の幅や奥行きを広げることを目的としています。顎の大きさや形態が狭すぎると、歯が並ぶスペースが足りず重なったり、前後にガタガタした歯並びになってしまい、不正咬合となります。
抜歯しないようにするアプローチ
将来的に抜歯しないで済む可能性を上げたり、後続の矯正治療をシンプルにするために床矯正を行います。低年齢からでも開始でき、取り外し可能な装置を使って、家庭でネジを巻くなどして徐々に顎を拡大していく方式が一般的です。歯を抜かないようにするという理念が大きく、顎の成長を利用する治療で補助的な矯正法とされることもあります。
床矯正の仕組みや使用装置の特徴
床矯正がどういう仕組みで働き、どのような装置を使うかが分かってくると、治療の特徴が見えてきます。
取り外し式装置であることが多い
床矯正で使われる装置は、口腔内の床(しょう)にあたる土台部分をもつ取り外し可能なプレート型装置が一般的です。装置には拡大ネジが組み込まれており、ネジを少しずつ回すことで装置が拡がり、その力で顎を外側に導く力を加えます。急速拡大装置を使用した後で、広がった顎を保定するタイミングであれば、ネジのない閉鎖型の床矯正を使用することもあります。
顎を拡げる力をかける方向
装置が拡がることで、上顎や下顎の横幅を広げ、歯が収まるスペースを確保します。ただし、装置の力のみで歯を動かすわけではなく、あくまで顎の成長や骨の適応及び変化を補助する役割を担います。
可撤式ゆえの利便性と制約
取り外し可能なことを可撤式(かてつしき)と言いますが、次のようなメリットと制約があります。
可撤式のメリット
- 装置を外してブラッシングでき、食べかすや歯垢(プラーク)を除去し、虫歯や歯周病に感染するリスクを抑えやすい
- 食事や発音などの際に一時的に装置を外せる
- 装置を清掃しやすい
可撤式の制約
- 子ども本人が装置を外す習慣がつくと、効果が減じる可能性がある
- 装置を扱い損ねると破損のおそれがある
床矯正のメリット・デメリット
床矯正を選ぶ際に押さえておきたい、主なメリットやデメリットを挙げていきましょう。
床矯正のメリット
床矯正のメリットは、適切な時期に開始し、正しい管理を行うことが前提となります。
極力歯を抜かずに矯正できる可能性が高まる
顎の幅を確保することで歯が生えるスペースができ、将来的に抜歯を回避できるケースもあります。
取り外し可能なので衛生管理がしやすい
装置を外して歯磨きや洗浄ができるため、虫歯や歯肉炎及び歯周病のリスクを低減します。
好きなものを食べられる
固定式の矯正装置では、固い食品や粘着性のある食べ物を控えなければならず、栄養バランスが偏りやすく、献立作りが大変になります。一方、床矯正は装置を取り外せるため、食事制限が少なく、子どもは好きなものを安心して食べられます。
見た目への影響が少ない
ワイヤーやブラケットと違い、目立ちにくいケースがあります。
顔つきや口元のバランス改善が期待できる
顎の成長誘導によって、フェイスラインのバランスが改善する可能性があります。
治療への理解や意識が得られる
顎を広げる一般的な床矯正装置の場合、ネジを巻くなど患者や保護者の協力が必要なため、治療への理解や意識が高まりやすくなります。
床矯正のデメリット
どんな治療法にもメリットのみではないように、床矯正にも、デメリットが存在します。十分な説明を聞いて理解したうえで、疑問点もなく納得された後に床矯正の治療を開始されることが望まれます。
患者の協力度やモチベーションに依存
装置を装着する時間やネジ操作を忘れたり、子供が嫌がるからと怠ると、装着時間が不足し、効果が出にくくなります。
すべての症例に対応できるわけではない
顎の変形が強い場合や、噛み合わせにも影響が及ぶ重度の不正咬合は、床矯正ではなく、通常のワイヤー矯正や外科矯正が必要になることがあります。
成長期を過ぎると効果が出にくくなる
顎骨の成長が止まりかけた年齢になると、顎の拡大力が制限されます。したがって、床矯正の開始時期の見極めが非常に重要です。
後戻りのリスク
拡げた顎や並んだ歯が後に元に戻ろうとする力が働くことがあります。これを防ぐため、保定期間や後続の治療が更に必要になることも考えられます。
装置の破損や管理コスト
取り扱いを誤ると破損してしまい、再製作や修理となり、時間や費用がかかることがあります。
顎を無理に拡げすぎるリスク
拡大力を過度にかけると、歯根の問題や歯茎への負担、骨性変形などを招く可能性も理論上否定できません。ただし、適切な設計や管理下で行えば可能性は低くなります。
床矯正の適用時期と適応条件
矯正歯科医がレントゲン、模型、口腔内観察などの検査を行ったうえで適応可能か、慎重に診断されます。床矯正を成功させやすい開始のタイミングと、適応の条件を確認しておきましょう。
開始のタイミング
最も効果的とされるのは 乳歯と永久歯が混在する混合歯列期で、小学校低学年から中学年くらいです。永久歯にすべて生え変わると、顎の発達やスペース確保が難しくなります。乳歯段階のうち、犬歯が生える前に始められると、少ない装置で済む可能性が高まるとしています。成長期を活用することで、顎骨の拡大が自然に行われやすいため、早期対応が望ましいとされます。
向き・不向きについて
床矯正が向くケース、反対に向かないケースを整理しましょう。
向くケース
- 顎の横幅がやや狭く、歯が生えるスペースが不足している
- 不正咬合の程度が比較的軽度~中等度である
- 患者さん本人や保護者に、装着する意志と管理のモチベーションがある
- 顎骨の成長する可能性が残っている年齢である
不向きもしくは注意が必要なケース
- 大きな上下顎のズレや顎変形がある
- 顎の幅の拡大だけでは対応困難な噛み合わせ異常である
- 成長期をほぼ過ぎていて顎骨変化が少ない年齢である
- 装着する意志や装置の管理が困難だと予想される
床矯正の治療の流れ
では、床矯正治療の流れをご紹介します。
- カウンセリング:歯並びの悩み、生活習慣、保護者の希望を聞き、治療の方向性を説明。
- 検査:口腔内診査や写真撮影、レントゲン撮影、模型作成、咬合力や姿勢チェック。
- 作成:検査データに基づき床矯正装置を作製し、ネジの位置や拡大量の設定などを調整。
- 装着:装置を口腔内に入れ、装着時間やネジ操作、清掃方法などを正しくを指導。
- 観察:1ヶ月程度で来院し、装置が正しく広がるか、むし歯や清掃状態などをチェック。
- 保定:拡大した顎や並んだ歯の維持に保定装置を使用し、後戻り対策と安定化を図る。
このように段階を踏み、安全性と効果を確保しながら治療を進めることが一般的です。
注意すべきこと
床矯正をうまく機能させるには、装置設計だけでなく、患者本人と保護者の協力が非常に重要です。それらを意識することが、成功率を上げます。
装着時間を守る
1日14時間以上の装着を行わなければなりません。この時間を守らないと、拡大力が十分に発揮できず、効果が減る可能性があります。
ネジ操作を確実に行う
ネジを回す操作を忘れたり、誤った方向に回したりしてしまうと、計画通りの拡大ができません。
装置を大切に扱う
乱暴に扱うと破損や変形につながります。破損すると修理や再製作が必要となり、手間や費用がかかり、治療期間も延長となります。
悪習慣の改善
口呼吸、指しゃぶり、頬杖、舌癖、姿勢の悪さなどはお口の周りの筋肉や顎の成長バランスに悪影響を及ぼします。床矯正とともに、これらの習慣除去を行うことが、治療効果を補強します。
保護者のサポートと管理
家庭での食事習慣やトレーニング、ネジ操作などのサポートは、装置の効果を最大限に引き出すために不可欠です。保護者が装置の管理をし、装着を促すことが適切に行えるかどうかが、治療成功へのポイントとも言えます。
定期チェックやメインテナンスを怠らない
定期的な来院をして調整を行わなければ、顎の拡大の進み具合が整わず不均一になるリスクがあります。
歯医者だけが歯並びを治すのではなく、患者さん本人と、保護者と歯科医師が協働して治す姿勢が、床矯正治療では特に重視されます。
他の小児矯正法との比較
床矯正は矯正治療のひとつのアプローチです。他の方法との比較を知っておくと、選択肢を判断する助けになります。
| 矯正法 | 主な特徴 | 強み | 弱み |
|---|---|---|---|
| ワイヤー矯正 (ブラケット法) |
歯の表面にブラケットとワイヤーを付け、歯を動かす | 幅広い症例に対応可能、制御性が高い | 装着感、見た目やケアの難しさ、抜歯を伴うこともあり |
| マウスピース矯正 (子ども用含む) |
透明な取り外し式のマウスピースで少しずつ歯を動かす | 見た目が目立ちにくい、取り外し可で衛生管理がしやすい | 顎骨の拡大には限界があり、適応症例が限定されることもあり |
| 拡大床矯正 (床矯正を含む) |
顎骨を広げ、スペースを確保する補助的な方法 | 顎骨誘導、抜歯回避に有利、早期介入可能 | 患者協力度依存や限界があり、すべての症例に適さない |
| 機能矯正装置 (ムーシールドなど) |
顎の筋機能や舌・口唇運動などを補助して矯正方向を誘導 | 筋機能改善を兼ね、早期の不正習癖に対応 | 顎の拡大力には制限、適応が限られる場合あり |
| 外科矯正 (顎変形治療など) |
骨切りなど手術を組み合わせて顎骨位置を修正 | 重度の不正咬合や顎変形も対応可能 | 高リスクや高コストで治療期間が長くなることが多い |
床矯正は、他の矯正法と併用されることも多く、特に 小児期の矯正で第Ⅰ期治療における顎骨誘導やスペース確保の役割を担うことが多いです。床矯正以外では、小児用マウスピース矯正のインビザラインファーストなどの選択肢もあります。
矯正治療の種類について選ぶときの注意点
- 上顎前突、反対咬合、叢生、開咬、過蓋咬合などの不正咬合の種類や程度はどの程度か
- 顎骨の発達についてまだ成長の余地はあるのか
- 患者さんや保護者が見た目、痛み、費用、通院頻度などについて希望はあるか
- 将来の矯正治療の負担や追加治療の可能性はあるのか
まとめ

床矯正は、子どもの成長期を活用して顎骨を適切に誘導し、将来の歯並び改善を図る補助的な矯正アプローチです。抜歯を減らし、見た目を抑え、衛生管理しやすくするなどのメリットがありますが、患者さん本人がきちんと協力できるか、治療開始時期、装置管理、後戻り対策などが成功を大きく左右します。治療を検討する際には、信頼できる矯正専門医とよく相談し、検査に基づいた計画を立ててもらうことが重要です。また、床矯正が万能ではないことを前提に、必要に応じて他の矯正法との併用も視野に入れながら判断するとよいでしょう。