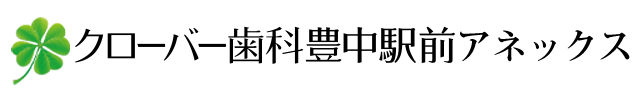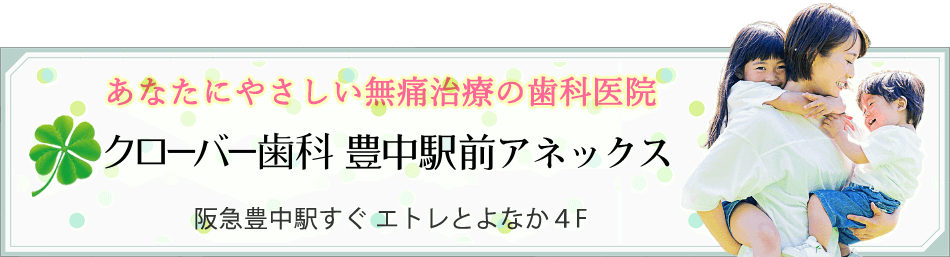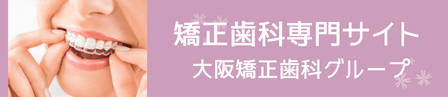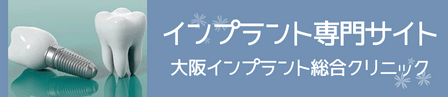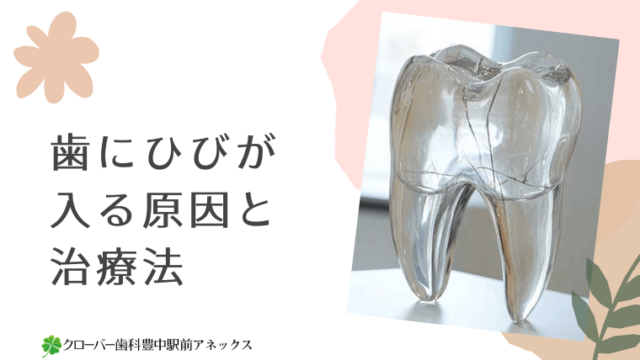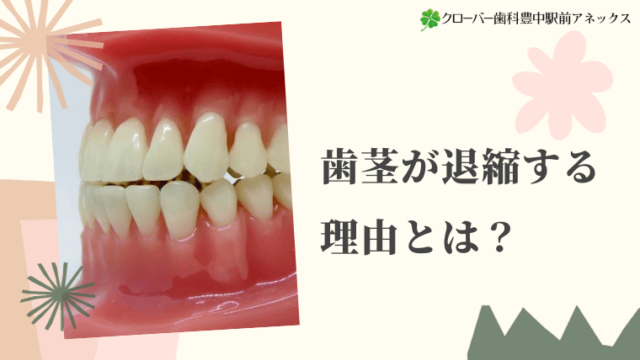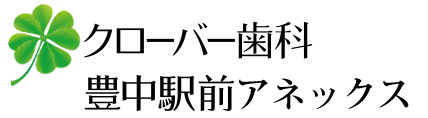歯のブリッジの寿命が来たら?再作製、修理、別治療への道
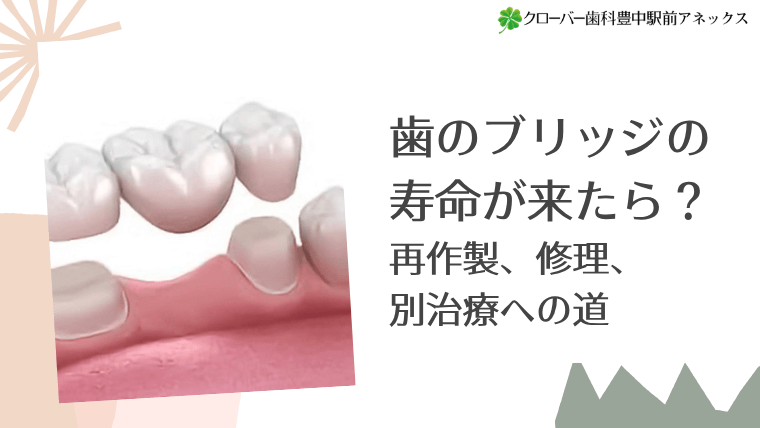
歯のブリッジの寿命が来たらどうすればよいのでしょうか。そもそも、歯のブリッジ治療とはどのようなものなのか、寿命が来たらしなければならない治療があるのかなど、詳しくご紹介いたします。
目次
歯のブリッジとは何か?
歯の治療において、失った歯を補う方法のひとつにブリッジ治療があります。失った歯の隣にある支えとなる健康な歯(支台歯)を両側または一側から削り、その上に連結した人工歯を橋のようにかぶせる橋渡しをすることで、欠損部を補う治療法です。
メリットとしては、比較的自然な噛み心地を得やすく、自分の歯のような見た目を維持しやすい点が挙げられます。また、保険適用範囲であればコストも抑えられる場合があります。ただしデメリットもあり、支えとなる歯を削る必要があること、清掃やメンテナンスがやや難しい構造となるため、長く使い続けるためには注意が必要です。
ブリッジの寿命はどれくらい?
まず目安となる歯のブリッジの寿命を知っておくことは重要です。一般的には、保険適用のブリッジであればおおよそ7~8年程度、セラミックの材料で作製した自由診療のものでは10年程度がひとつの目安となります。ただし、これはあくまで目安であり、お口の環境によって大きく変わってきます。
- 口腔内の清掃状態、歯周病や虫歯の有無
- 噛む力や噛み合わせの状態
- ブリッジの素材や設計、支えとなる歯の状態
- 定期的なメンテナンスの実施の有無
清掃もしっかり行い、定期的にメンテナンスも実施している口腔状態が良好な方では、10年以上持続するケースも報告されています。反対に口腔ケアが不十分だったり、噛み合わせに問題があると、3年ほどで寿命を迎えてしまうというケースもあります。寿命を見極めるためには、自分のブリッジがどれくらい使われてきたか、どのような使われ方をしてきたかを振り返ることが大切です。
寿命が来たらってどんな感じ?サインとは?
歯のブリッジの寿命が来たらどうする?という点には、寿命が近づいてきている、限界が来ているというサインを見逃さないことが非常に重要です。今から挙げるトラブルがある場合、早めの対応を検討してください。
ブリッジが欠けたり割れたりしている
ブリッジが外れたり、ガタついている
支えている歯が虫歯になっている
噛んだ時に不快感や痛みが歯茎や隣の歯にある
口臭や嫌な臭いがし、食べカスが溜まりやすい感覚がある
ブリッジが欠けたり割れたりしている
ブリッジ本体が欠けたり、割れたりするのは明らかに寿命が来ているサインです。接着剤や被せの劣化によって、構造的な強度が落ちてきている場合があります。
ブリッジが外れたり、ガタついている
支えとなる歯が少しずつ動いたり、歯茎が変化したりすることできつくはまっていたブリッジがゆるくなることがあります。
支えている歯が虫歯になっている
ブリッジの構造上、どうしても清掃が難しい部分があります。支えている歯が虫歯や歯周病になってしまうと、ブリッジ全体の寿命が短くなってしまいます。
噛んだ時に不快感や痛みが歯茎や隣の歯のあたりにある
噛んだ時の違和感、歯茎が腫れている感じ、隣の歯に比べて噛む力が弱い感じがする時も、構造に問題が出てきている可能性があります。
口臭や嫌な臭いがし、食べカスが溜まりやすい感覚がある
ブリッジと、歯茎や隣接歯との間に隙間ができると、食べカスが入り込みやすくなり、細菌が繁殖し口臭の原因になったりします。
このようなサインを自覚したら、そろそろ寿命が来たかもしれない、次を考えるべきだと判断し、歯科医院での診断や相談をおすすめします。
寿命を迎えたブリッジに起こりうるリスク
ブリッジの寿命が来たまま放置すると、単に噛みにくくなるのみで済まないケースもあり、口腔内のリスクが増大します。
虫歯の進行・痛みのリスク
ブリッジの支えとなる歯が虫歯になっても、神経を既に抜いた抜髄という処置がされていれば痛みを感じにくく、気づかないうちに進行してしまいます。最悪の場合は抜歯が必要になることがあります。
支えとなる健康な歯への負担増加
ブリッジで支えている隣の歯には常に負担がかかります。欠損部分の咬合力を支台歯で補わなければならず、長期間使うほど、支台歯自体が劣化や損傷を受けやすくなり、全体の歯列の健康が損なわれることがあります。
清掃困難による衛生状態の悪化
ブリッジは連結構造ゆえに歯間や歯茎の境目、隣接歯との隙間など清掃しづらい箇所が出てきます。そのため、歯周病や虫歯のリスクが高まり、結果としてブリッジの寿命も縮まってしまいます。
噛み合わせの崩れや顎関節への影響
支台歯、歯茎、骨の状態が悪化すると、噛み合わせが変化するリスクがあります。噛み合わせが悪化すると、顎関節に負担がかかってしまい、隣接歯や反対側の歯への影響が出て、顎関節症のリスクも高くなります。
寿命が来たらどうすればよいのかという問題に対しては、ただブリッジをやり直すというものではなく、口全体の歯の健康、噛み合わせ、将来の治療を含めて次を考えるきっかけとなります。
寿命が来たら考えるべき治療の選択肢
ブリッジの寿命が来てしまったり、来そうだと感じたときに、どのような選択肢があるのでしょうか。
再装着や修理
ブリッジが外れただけ、あるいは欠けが軽度であれば、再装着や部分修理で継続使用できる場合があります。とはいえ、修理済みのものは耐久性がやや劣るため、近い将来再作製しなければならないというのを前提として暫定的な対応と考えるのが良いでしょう。
ブリッジの再作製
支台歯の状態が良好で、残存歯や歯根に問題がない場合、新たにブリッジを作り直す選択肢があります。以前の問題点を踏まえ、素材、設計、噛み合わせなどを改善することで、より長持ちさせることを目指します。ただし、支台歯が病変していたり、歯が必要であったり、歯根が損傷している場合は、この選択が難しいです。
インプラントや入れ歯への切り替え
支えとなる歯が使えない、歯根が無くなってしまった、あるいは将来的なメンテナンス性や負担を考慮して別の治療を検討する場合、インプラントや入れ歯への切り替えも選択肢となります。
| 治療法 | 構造・仕組み | 他の歯への影響 | 保険適用 | 主なメリット | 主なデメリット |
|---|---|---|---|---|---|
| インプラント | 欠損部分の顎骨に人工歯根(チタン)を埋入し、骨と結合後に人工歯を装着する | 他の歯を削らない | 自由診療 | 見た目や噛み心地が天然歯に近く、周囲の歯への負担がなく長持ちしやすい | 費用が高く外科手術が必要で治療期間が長い |
| ブリッジ | 欠損部の両隣の歯を削って支台にし, 橋のように人工歯をかける | 両隣の健康な歯を削る必要がある | 保険適用あるが素材により自由診療も可 | 固定式で安定感があり、装着感が自然で比較的短期間で治療 | 支えの歯に負担がかかり清掃が難しく、寿命がある |
| 入れ歯 | 取り外し式の人工歯で欠損を補い、部分入れ歯は金属バネで固定し、総入れ歯は歯茎全体に装着 | 部分入れ歯の場合隣の歯にバネをかけるため負担あり | 保険・自由診療どちらもあり | 費用が比較的安くほとんどの症例で対応可能で短期間で治療 | 噛み心地がやや劣り違和感やズレが出やすく、定期調整が必要 |
それぞれ、費用や治療期間、口腔内の条件が異なりますので、歯科医師と十分に相談のうえ、ライフスタイルや将来への予測も含めて検討することが大切です。
寿命を延ばすためのケアやメンテナンス方法
まだ寿命は来ていないが長く使いたいけれど、寿命を迎える時に少しでも先延ばしにしたいという方のために、ケア方法を取り入れることをおすすめします。
専用ケアグッズの使用
ブリッジの構造上、通常の歯ブラシだけでは磨きづらい部分があります。歯間ブラシ、フロス、タフトブラシなどを使用することで、歯と歯の間、歯茎の境目、ブリッジの端部などの磨き残しを防ぎやすくなります。
歯科医院での定期的なクリーニング/メンテナンス
プロによる定期的クリーニングを受けることで、歯やブリッジの周囲にこびりついたバイオフィルムを除去でき、虫歯や歯周病のリスクを低減できます。また、噛み合わせのチェックやブリッジ、支台歯の状態を歯科医師が確認することで、早期対応につながります。
ナイトガードの使用
歯ぎしりや食いしばりがある方は、夜間に歯やブリッジに過度な咬合力がかかってしまうことがあります。睡眠時に装着するナイトガードを使用すれば、力を分散でき、歯やブリッジを保護し、構造の劣化を遅らせる効果が期待できます。
食生活や噛み方に気をつける
硬すぎる氷やナッツ、粘着性の強いガムや飴などは、ブリッジに過度な負荷をかける可能性があります。頻繁に好んで食べる習慣があると、ブリッジは早めに寿命を迎えることもあります。どうしても食べたい場合は小さく切って食べたり、硬い食べ物はやめて柔らかめの食べ物を選ぶといった配慮も寿命の延長につながります。
まとめ

ブリッジは決して永久に使えるわけではなく、平均的には保険適用で7~8年、自由診療で10年前後がひとつの目安です。寿命が近づいてきたり、限界が来たと感じるサインとして、割れや外れ、支台歯の虫歯や不快感、臭いなどがあります。そのまま放置すると、過度な負荷による支台歯の抜歯、歯列全体への影響、噛み合わせの崩れなど治療が必要になるリスクが増えます。
選択肢としては修理や再装着、再製作、インプラントか入れ歯への切り替えがあり、支台歯や歯根、口腔全体の条件に応じて歯科医師と相談することが大切です。寿命を延ばすためには、ケアグッズの使用による清掃、定期的なプロのクリーニング、ナイトガード、食生活の見直しなどが有効です。自分の口の中の状態を知り、早めに異変をキャッチして、将来を見据えた治療やケアを行うことが最も重要と言えます。